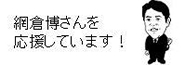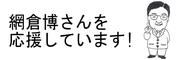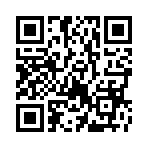2010年06月20日
11.「漫画と小学生の非常識な関係」
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

「何でも、親の悪いところばかり、真似をする」
このようなご意見を、お母さんお父さんから、よく聞きます。
良いところは、全然似てくれないのに、
「お父さんのだらしないところ」など、似て欲しくないところばかり、似てしまうというのです。
かなり、耳の痛い話です。(泣)
さて、それはさておき、子どもは、
モデリング
<人および動物が他者の行動(モデル)を観察することによって、その行動の全体、
あるいは部分と類似した行動を繰り返すことをさす 辞書より> の天才です。
悪い事を、真似をされないことに、ビクビクしてしまったり、
真似させないことに注意を向けるより、子どもが真似する天才である特性を、
上手く使う方法を、一緒に考えましょう。
実は、子どもは、モデリングの天才なので、
この特性を使わない手はないのです。
つまり、真似して欲しい、人物の情報を、
子どもに伝えることで、子どものモデリング力を、最大限有効活用し、望ましいと思われる状況に、
自然と導くことができるのです。
これが、私が考えている仮説であり、日々実践している事です。
たとえば、1970年代に生まれた世代が、
(川口能活さん、小野伸二さん、中田英寿さんなど)、
日本のサッカーのレベルを大きく引き上げたのは、
あまりにも有名な事実です。
そして、そんな彼らがモデリングしたのは、
「キャプテン翼」というサッカー漫画なのです。
主人公キャプテン翼に、あこがれて、
彼が漫画の中で行う、さまざまな技を、真似したり、ボールが顔にぶつかっても、
「ボールは友達・・・」と、
再TRYするなど、サッカーを通じ、
生きて行くのに必要な、友情や一生懸命することを、学んだ子どもは、本当に、多かったのです。
この情報化社会の中では、
お母さんお父さんが、戦略的に、モデリングさせたい人物像を、あれば、
まずは、その人物像を明確することが重要です。
※ 漫画だけではなく、小説や、本や、映画や、スポーツ選手や、芸術家や、音楽家や、政治家や、
インターネット上の中から、選択する。
その上で、それらの情報を、意識的に多く、子どもに浴びさせることで、
子どものモデリングは、はじまるのです。
もちろん、お母さんお父さん(特に、お父さん)が、
子どもの見本になってあげられれば、本当は良いのですが、
私たちお母さん、お父さんだって、不得意分野もあるのです。
不得意分野では、お母さんお父さんは、勝負せず、
モデリングで、子どもの特性を有効活用し、そして、お母さんお父さんが、得意な分野で勝負する。
そんなやり方も、楽しいかもしれません。子どもはモデリングの天才。
覚えておいて損はない情報です。
お母さん、お父さん、日々実践。
私も、がんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

「何でも、親の悪いところばかり、真似をする」
このようなご意見を、お母さんお父さんから、よく聞きます。
良いところは、全然似てくれないのに、
「お父さんのだらしないところ」など、似て欲しくないところばかり、似てしまうというのです。
かなり、耳の痛い話です。(泣)
さて、それはさておき、子どもは、
モデリング
<人および動物が他者の行動(モデル)を観察することによって、その行動の全体、
あるいは部分と類似した行動を繰り返すことをさす 辞書より> の天才です。
悪い事を、真似をされないことに、ビクビクしてしまったり、
真似させないことに注意を向けるより、子どもが真似する天才である特性を、
上手く使う方法を、一緒に考えましょう。
実は、子どもは、モデリングの天才なので、
この特性を使わない手はないのです。
つまり、真似して欲しい、人物の情報を、
子どもに伝えることで、子どものモデリング力を、最大限有効活用し、望ましいと思われる状況に、
自然と導くことができるのです。
これが、私が考えている仮説であり、日々実践している事です。
たとえば、1970年代に生まれた世代が、
(川口能活さん、小野伸二さん、中田英寿さんなど)、
日本のサッカーのレベルを大きく引き上げたのは、
あまりにも有名な事実です。
そして、そんな彼らがモデリングしたのは、
「キャプテン翼」というサッカー漫画なのです。
主人公キャプテン翼に、あこがれて、
彼が漫画の中で行う、さまざまな技を、真似したり、ボールが顔にぶつかっても、
「ボールは友達・・・」と、
再TRYするなど、サッカーを通じ、
生きて行くのに必要な、友情や一生懸命することを、学んだ子どもは、本当に、多かったのです。
この情報化社会の中では、
お母さんお父さんが、戦略的に、モデリングさせたい人物像を、あれば、
まずは、その人物像を明確することが重要です。
※ 漫画だけではなく、小説や、本や、映画や、スポーツ選手や、芸術家や、音楽家や、政治家や、
インターネット上の中から、選択する。
その上で、それらの情報を、意識的に多く、子どもに浴びさせることで、
子どものモデリングは、はじまるのです。
もちろん、お母さんお父さん(特に、お父さん)が、
子どもの見本になってあげられれば、本当は良いのですが、
私たちお母さん、お父さんだって、不得意分野もあるのです。
不得意分野では、お母さんお父さんは、勝負せず、
モデリングで、子どもの特性を有効活用し、そして、お母さんお父さんが、得意な分野で勝負する。
そんなやり方も、楽しいかもしれません。子どもはモデリングの天才。
覚えておいて損はない情報です。
お母さん、お父さん、日々実践。
私も、がんばります。
2010年06月19日
10.「英語ができるふりをする、5つの実践アイデア」
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

前回第9回は、
「子どもが、英語を楽しそうに、無理なく話し出す、最も簡単な方法」
について、お話しました。
そして、そのポイントは、
「私たちお母さん、お父さんが、いかに楽しそうに英語を使って、
海外の人たちと話す姿を、子どもたちに見せたり、そのようなふりをするかが、大事」
ということを、お話しました。
今日は、我が家で、また同じような考えで、
「英語を話すふりをしているお母さんお父さんのやり方」を、ご紹介していきます。
1.お母さん、お父さんが、英語教室にいく。
子どもを英語教室に行かせる、お母さん、お父さんは、
よく聞きますが、自ら実践! ということで、英語教室に行っている
お母さん、お父さんの話はあまり聞きません。
市で開催している英語教室、教会で開催している英語教室など、
安くても学べるところは、たくさんではないですが、結構あるそうです。
市役所発行の広報や、情報通のお母さん、お父さんの情報を手に入れ、
ぜひ通ってみましょう。
2.レアジョブを使ってオンライン勉強
なかなか、外にでて勉強する時間がない、
お母さん、お父さんには、インターネットでスカイプなどを、使って英語を学ぶことができる。
有名な所は、レアジョブ。
フィリピンの大学生と英会話レッスンをするのですが、
魅力なのは、かなりの低価格で、英会話を学べること。
子どもがお休みの土日などに、一緒に学んでも、面白いかもしれない。
3.英語の本、地図、地球儀を買う
インターネットの本屋さん、アマゾンなどを、使用すれば、
今は洋書も、手に入ります。
しかも、中には、金額がかなり安い物なども、あるのです。
洋書を買って誰が、読むの? というと、
読まないでもOKなのです。
なにせ、「英語を話せる、読めるふりをすればいい」
ので、インテリアとして、飾っておくだけでも、効果があるでしょう。
4.海外のテレビ番組を見る
有名な所ではCNNなど、海外のニュース番組などを、
聞いているふりをするのも、お勧めです。
子どもがいる時間帯とすると、
NHKのBSで、朝6時~8時までやっている、
「おはよう世界」などは、お勧め。
テレビが嫌なお母さん、お父さんは、音声だけでも流しておくと、
良いかもしれません。
5.CDなどを、流しておく
英語は耳からという言葉もあるように、CDなどを、流しっぱなしにして、
お母さんお父さんは、BGMとして流しておき
(意味がわからないですが、BGMになるので、仕事もはかどります)
おくことも、有効です。
しばらくすると、子どもは耳が良いので、
聞き取り口ずさむようになります。
などなど、大事な事は、英語アレルギーを、
お母さんお父さんが子どもに見せないことですので、気楽に使えるものがあれば、
TRY&ENJOYしてみて下さい。
お母さん、お父さん、日々実践。
私も、がんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

前回第9回は、
「子どもが、英語を楽しそうに、無理なく話し出す、最も簡単な方法」
について、お話しました。
そして、そのポイントは、
「私たちお母さん、お父さんが、いかに楽しそうに英語を使って、
海外の人たちと話す姿を、子どもたちに見せたり、そのようなふりをするかが、大事」
ということを、お話しました。
今日は、我が家で、また同じような考えで、
「英語を話すふりをしているお母さんお父さんのやり方」を、ご紹介していきます。
1.お母さん、お父さんが、英語教室にいく。
子どもを英語教室に行かせる、お母さん、お父さんは、
よく聞きますが、自ら実践! ということで、英語教室に行っている
お母さん、お父さんの話はあまり聞きません。
市で開催している英語教室、教会で開催している英語教室など、
安くても学べるところは、たくさんではないですが、結構あるそうです。
市役所発行の広報や、情報通のお母さん、お父さんの情報を手に入れ、
ぜひ通ってみましょう。
2.レアジョブを使ってオンライン勉強
なかなか、外にでて勉強する時間がない、
お母さん、お父さんには、インターネットでスカイプなどを、使って英語を学ぶことができる。
有名な所は、レアジョブ。
フィリピンの大学生と英会話レッスンをするのですが、
魅力なのは、かなりの低価格で、英会話を学べること。
子どもがお休みの土日などに、一緒に学んでも、面白いかもしれない。
3.英語の本、地図、地球儀を買う
インターネットの本屋さん、アマゾンなどを、使用すれば、
今は洋書も、手に入ります。
しかも、中には、金額がかなり安い物なども、あるのです。
洋書を買って誰が、読むの? というと、
読まないでもOKなのです。
なにせ、「英語を話せる、読めるふりをすればいい」
ので、インテリアとして、飾っておくだけでも、効果があるでしょう。
4.海外のテレビ番組を見る
有名な所ではCNNなど、海外のニュース番組などを、
聞いているふりをするのも、お勧めです。
子どもがいる時間帯とすると、
NHKのBSで、朝6時~8時までやっている、
「おはよう世界」などは、お勧め。
テレビが嫌なお母さん、お父さんは、音声だけでも流しておくと、
良いかもしれません。
5.CDなどを、流しておく
英語は耳からという言葉もあるように、CDなどを、流しっぱなしにして、
お母さんお父さんは、BGMとして流しておき
(意味がわからないですが、BGMになるので、仕事もはかどります)
おくことも、有効です。
しばらくすると、子どもは耳が良いので、
聞き取り口ずさむようになります。
などなど、大事な事は、英語アレルギーを、
お母さんお父さんが子どもに見せないことですので、気楽に使えるものがあれば、
TRY&ENJOYしてみて下さい。
お母さん、お父さん、日々実践。
私も、がんばります。
2010年06月16日
9.子どもが英語を楽しそうに、無理なく話しだす最も簡単な方法
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

私には、今現在10歳以下の子どもが、一人います。
そして、彼女には、将来英語は、もちろん、
中国語など、いろいろな語学をあやつり、世界のたくさんの人たちと、
コミュニケーションをして欲しいと、考えています。
どうでしょうか?
お母さん、お父さんの中にも、私と同じような気持ち、
希望を持っていらっしゃる方は、多いかもしれないと考えています。
では、「子どもが、英語を楽しそうに、無理なく話し出す、最も簡単な方法」
が、あればどうでしょうか?
試してみたくは、ないですか?
そのために、私たち、お母さん、お父さんができることを、
今日は、お話していきたいと思います。
通常で考えると、
多くのお母さん、お父さんは、そのために、
子どもを英語塾に行かせたり、
家庭教師をつけたり、
小さいころから、英語に触れさせたりすることが、
重要だ、必要だと、
考えるかもしれません。
しかし、私は、英語塾に通わせることなどは、
あまり重要な事ではないと、考えています。
では、何が重要か?
それは、子ども自身が、
「英語で海外の人たちとお話するのは、本当に楽しい」、
「中国語で、アジアの人たちと話すことが、楽しい」
と、心の底から思うことができる環境を作ることが、
とても重要だと考えています。
なぜなら、子どもは、楽しいことは、
勝手に自ら学習するように、なるからです。
反対に、嫌々英語を習っていても、
それは嫌いになっていってしまうと思うからです。
つまり、子どもが楽しく語学をするために、
最も有効で、最も効果があるのは、
実は、私たちお母さんお父さんが、
「楽しそうに、英語を使って、海外の人たちと、話す姿を子どもたちに見せたり」、
「私のように話せない人は、楽しそうに、話せるふりを、したり」、
「海外の情報にも、興味をもったり、興味を持っているふりをしたり」
することだと思うのです。
なぜなら、
子どもは、最も親に影響されるからです。
子どもを塾に行かせるより、もっと重要なのは、
英語が話せるふりをして、
(ふりでOKだよ。頑張っている姿を子どもに、みせるのが重要だよ)
楽しそうに、海外の人と、コミュニケーションをとる事だったり、
学び続ける姿勢を見せる事だったり、するのです。
政治家の子どもは、政治家になり、
医者の子どもは、医者になり、経営者の子どもは、経営者になる。
このような傾向が、あるのは、確かですが、
その子どもは、親の職業の素質が生まれつきあるのか?
というと、そのようなことは、ありません。
日々の親の姿をみて
、その考え方、感じ方、行動を、毎日の生活の中で、モデリングし、
そのよになるのです。
英語を楽しそうに話せるふりで、行きましょう。
お母さん、お父さん、日々実践。
私も、がんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

私には、今現在10歳以下の子どもが、一人います。
そして、彼女には、将来英語は、もちろん、
中国語など、いろいろな語学をあやつり、世界のたくさんの人たちと、
コミュニケーションをして欲しいと、考えています。
どうでしょうか?
お母さん、お父さんの中にも、私と同じような気持ち、
希望を持っていらっしゃる方は、多いかもしれないと考えています。
では、「子どもが、英語を楽しそうに、無理なく話し出す、最も簡単な方法」
が、あればどうでしょうか?
試してみたくは、ないですか?
そのために、私たち、お母さん、お父さんができることを、
今日は、お話していきたいと思います。
通常で考えると、
多くのお母さん、お父さんは、そのために、
子どもを英語塾に行かせたり、
家庭教師をつけたり、
小さいころから、英語に触れさせたりすることが、
重要だ、必要だと、
考えるかもしれません。
しかし、私は、英語塾に通わせることなどは、
あまり重要な事ではないと、考えています。
では、何が重要か?
それは、子ども自身が、
「英語で海外の人たちとお話するのは、本当に楽しい」、
「中国語で、アジアの人たちと話すことが、楽しい」
と、心の底から思うことができる環境を作ることが、
とても重要だと考えています。
なぜなら、子どもは、楽しいことは、
勝手に自ら学習するように、なるからです。
反対に、嫌々英語を習っていても、
それは嫌いになっていってしまうと思うからです。
つまり、子どもが楽しく語学をするために、
最も有効で、最も効果があるのは、
実は、私たちお母さんお父さんが、
「楽しそうに、英語を使って、海外の人たちと、話す姿を子どもたちに見せたり」、
「私のように話せない人は、楽しそうに、話せるふりを、したり」、
「海外の情報にも、興味をもったり、興味を持っているふりをしたり」
することだと思うのです。
なぜなら、
子どもは、最も親に影響されるからです。
子どもを塾に行かせるより、もっと重要なのは、
英語が話せるふりをして、
(ふりでOKだよ。頑張っている姿を子どもに、みせるのが重要だよ)
楽しそうに、海外の人と、コミュニケーションをとる事だったり、
学び続ける姿勢を見せる事だったり、するのです。
政治家の子どもは、政治家になり、
医者の子どもは、医者になり、経営者の子どもは、経営者になる。
このような傾向が、あるのは、確かですが、
その子どもは、親の職業の素質が生まれつきあるのか?
というと、そのようなことは、ありません。
日々の親の姿をみて
、その考え方、感じ方、行動を、毎日の生活の中で、モデリングし、
そのよになるのです。
英語を楽しそうに話せるふりで、行きましょう。
お母さん、お父さん、日々実践。
私も、がんばります。
2010年05月24日
8.100倍、子どもに伝わる、魔法のコミュ術、3つのポイント
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

「くずくず、だらだらしている」、
「何度いっても、言う事を聞かない」、
「悪ふざけをやめない」、
「ふぇんふぇん。泣きやまない」、
「頑なに、黙りこくっている」
子どもが、お母さん、お父さんの意に反し、
このような態度を取り続けることが、あるかもしれません。
そんな時、私たちは、
どうしても、私たち自身の考えている事が、子どもに伝わっていないと理解し、
そして、もっと子どもに伝えなければと、
頑張ってしまうことになります。
しかし、頑張れば、頑張るほど、
お母さん、お父さんが伝えたい事は、伝わらなくなります。
そして、希望する方向の逆に行くことに、なるのです。
今日は、
お母さん、お父さんが、本当に大事なことを、
子どもに伝える時に、
実践していただきたい、3つのポイントをご紹介します。
ポイント1 大事な事は、低い声で言う
お母さん、お父さんが、子どもに
「言いたい事が伝わっていない」と思う時、
私たちはどうしても、かなり高い声を、出してしまいます。
子どもとすると、
「キャーキャー」と興奮してなにか、お母さんが言っているとしか、
感じない状態になっているケースが、多いのです。
上手く伝わらないな~。
声が少し高すぎるのかな?
と感じた時は、少し、低いドスの利いた声で話をしてみてください。
効果があるはずです。
ポイント2 大事なことは、小さな声で言う
お母さん、お父さんが、子どもに
「言いたい事が伝わっていない」と思う時、
私たちはどうしても、隣の家に聞こえそうな大きな声で、
子どもに話してしまいます。
しかし、大きな声で怒鳴られた瞬間、本能的に
「言葉を理解するより、逃げたい意識になりますので、かえって逆効果なのです」
大事な事は、小さな声で言い、
子どもに聞きたいと、思わせるのが鉄則です。
ポイント3 大事な事は、ゆっくり言う。
お母さん、お父さんが、子どもに
「言いたい事が伝わっていない」と思う時、私たちはどうしても、
あれもこれもと、どんどん早口になります。
しかし、これも、逆効果です。
大事なことこそ、子どもだからこそ、
相手が理解できるかなり、ゆっくり言うことが重要です。
(ゆっくりした英語は、聞き取れるけど、ネイティブの早さの英語はお手上げと同じです)
私の本業は、経営者・経営幹部の方に、
世界で使えるコミュニケーションを、ご紹介することです。
コミュニケーションの上手い社長さんほど、
重要でどうしても伝えたい話をするときは、
1.社員の方に、重みのある低いどっしりとした声で、
2.社員の方が集中したくなるような、多少小さな声で、
3.噛みしめて理解できるような、ゆっくりとしたリズムで、
お話をすることが、多いのです。
お母さん、お父さん、日々実践。
私も、がんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

「くずくず、だらだらしている」、
「何度いっても、言う事を聞かない」、
「悪ふざけをやめない」、
「ふぇんふぇん。泣きやまない」、
「頑なに、黙りこくっている」
子どもが、お母さん、お父さんの意に反し、
このような態度を取り続けることが、あるかもしれません。
そんな時、私たちは、
どうしても、私たち自身の考えている事が、子どもに伝わっていないと理解し、
そして、もっと子どもに伝えなければと、
頑張ってしまうことになります。
しかし、頑張れば、頑張るほど、
お母さん、お父さんが伝えたい事は、伝わらなくなります。
そして、希望する方向の逆に行くことに、なるのです。
今日は、
お母さん、お父さんが、本当に大事なことを、
子どもに伝える時に、
実践していただきたい、3つのポイントをご紹介します。
ポイント1 大事な事は、低い声で言う
お母さん、お父さんが、子どもに
「言いたい事が伝わっていない」と思う時、
私たちはどうしても、かなり高い声を、出してしまいます。
子どもとすると、
「キャーキャー」と興奮してなにか、お母さんが言っているとしか、
感じない状態になっているケースが、多いのです。
上手く伝わらないな~。
声が少し高すぎるのかな?
と感じた時は、少し、低いドスの利いた声で話をしてみてください。
効果があるはずです。
ポイント2 大事なことは、小さな声で言う
お母さん、お父さんが、子どもに
「言いたい事が伝わっていない」と思う時、
私たちはどうしても、隣の家に聞こえそうな大きな声で、
子どもに話してしまいます。
しかし、大きな声で怒鳴られた瞬間、本能的に
「言葉を理解するより、逃げたい意識になりますので、かえって逆効果なのです」
大事な事は、小さな声で言い、
子どもに聞きたいと、思わせるのが鉄則です。
ポイント3 大事な事は、ゆっくり言う。
お母さん、お父さんが、子どもに
「言いたい事が伝わっていない」と思う時、私たちはどうしても、
あれもこれもと、どんどん早口になります。
しかし、これも、逆効果です。
大事なことこそ、子どもだからこそ、
相手が理解できるかなり、ゆっくり言うことが重要です。
(ゆっくりした英語は、聞き取れるけど、ネイティブの早さの英語はお手上げと同じです)
私の本業は、経営者・経営幹部の方に、
世界で使えるコミュニケーションを、ご紹介することです。
コミュニケーションの上手い社長さんほど、
重要でどうしても伝えたい話をするときは、
1.社員の方に、重みのある低いどっしりとした声で、
2.社員の方が集中したくなるような、多少小さな声で、
3.噛みしめて理解できるような、ゆっくりとしたリズムで、
お話をすることが、多いのです。
お母さん、お父さん、日々実践。
私も、がんばります。
2010年05月21日
7.「カンニングしよう」 子どもの地図をカンニングしよう。
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

「楽しく、愉快な毎日を過ごしたい。」
多くのお母さん、お父さんは、このように考えていますよね。
そんなお母さん、お父さんに、
今日は、「心をカンニングする」という、
裏技をご紹介します。
私は、本業で、出版社の代表をしていまして、
世界中から、人間関係をより良いものにしていく、コミュニケーションスキルを、
集め経営者の方に、ご紹介することを、仕事にしています。
そして、
「これらのコミュニケーションスキル」
が、お母さん、お父さんに、とても、お役に立てると、思うのです。
多くのお母さん、お父さんは、
コミュニケーションで、最も重要なことは、
「子どもに、何を伝えるべきか?」だと、誤解されています。
しかし、本当に重要なことは、実は、違うのです。
「何を伝えるべきか?」ではなく、
その内容が、子どもに、「どのように伝わったのか?」なのです。
誤解を恐れず言えば、
お母さんお父さんが言いたい事が、結果的に、子どもに伝わっていれば、
お母さんお父さんが、無言であっても、
何を伝えるべきかに、
力をかけすぎなくてもOKなのです。
現在多くの、お母さんお父さんが、
子どもとのコミュニケーションで、なかなか上手く、子どもに伝わらないと、
悩んでいると言われてます。
そして、その解決策として、
お母さん同志、お母さんお父さんで、話あい、
「なんて言ったら、わかるのかな」
と、試行錯誤していらっしゃいます。
しかし、お母さんお父さんは、
子どもに戻ることはできませんので、
どうしても本当の子どもの気持ちは、分からないのです。
コミュニケーションで重要なのは、
「何を言うべきか?」ではなく、「どのように伝わったか?」なので、
私は、「子どもに、自分の気持ちが伝わらないな・・・」と言う時は、
子ども本人に、「どのように感じているの?」と、
聞いてしまうことに、しています。
子どもに聞いてもOKですし、
近所の子どもたち、
子どものいとこたち、
子どもの友人たちに、
「お母さんに、○○と言われたら、どのように感じるの?教えてくれる?」、
「○○の時、どんな感じがするのかな?」、
「どのように言われたら、やる気になるかな?」など、
具体的に聞いてしまっても、OKだと思います。
お母さんお父さんは、
真面目な方が多く、私がこのように、「子どもの気持ちをカンニングしましょう」と、
ご提案しても、なかなか、カンニングしていただけません。(泣)
でも、お母さんお父さんの価値観だけで、
「あれこれ」「いろいろ」子どもの気持ちを想像して、
何を言うべきかを考えることに、付け加えて、
「子どもに、直接聞いてしまう」というやり方も、
時には、思い出していただき、考えて実践してみていただけたら、
子ども喜ぶと思います。
ぜひ、お勧めいたします。
お母さん、お父さん、日々実践。私も、がんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

「楽しく、愉快な毎日を過ごしたい。」
多くのお母さん、お父さんは、このように考えていますよね。
そんなお母さん、お父さんに、
今日は、「心をカンニングする」という、
裏技をご紹介します。
私は、本業で、出版社の代表をしていまして、
世界中から、人間関係をより良いものにしていく、コミュニケーションスキルを、
集め経営者の方に、ご紹介することを、仕事にしています。
そして、
「これらのコミュニケーションスキル」
が、お母さん、お父さんに、とても、お役に立てると、思うのです。
多くのお母さん、お父さんは、
コミュニケーションで、最も重要なことは、
「子どもに、何を伝えるべきか?」だと、誤解されています。
しかし、本当に重要なことは、実は、違うのです。
「何を伝えるべきか?」ではなく、
その内容が、子どもに、「どのように伝わったのか?」なのです。
誤解を恐れず言えば、
お母さんお父さんが言いたい事が、結果的に、子どもに伝わっていれば、
お母さんお父さんが、無言であっても、
何を伝えるべきかに、
力をかけすぎなくてもOKなのです。
現在多くの、お母さんお父さんが、
子どもとのコミュニケーションで、なかなか上手く、子どもに伝わらないと、
悩んでいると言われてます。
そして、その解決策として、
お母さん同志、お母さんお父さんで、話あい、
「なんて言ったら、わかるのかな」
と、試行錯誤していらっしゃいます。
しかし、お母さんお父さんは、
子どもに戻ることはできませんので、
どうしても本当の子どもの気持ちは、分からないのです。
コミュニケーションで重要なのは、
「何を言うべきか?」ではなく、「どのように伝わったか?」なので、
私は、「子どもに、自分の気持ちが伝わらないな・・・」と言う時は、
子ども本人に、「どのように感じているの?」と、
聞いてしまうことに、しています。
子どもに聞いてもOKですし、
近所の子どもたち、
子どものいとこたち、
子どもの友人たちに、
「お母さんに、○○と言われたら、どのように感じるの?教えてくれる?」、
「○○の時、どんな感じがするのかな?」、
「どのように言われたら、やる気になるかな?」など、
具体的に聞いてしまっても、OKだと思います。
お母さんお父さんは、
真面目な方が多く、私がこのように、「子どもの気持ちをカンニングしましょう」と、
ご提案しても、なかなか、カンニングしていただけません。(泣)
でも、お母さんお父さんの価値観だけで、
「あれこれ」「いろいろ」子どもの気持ちを想像して、
何を言うべきかを考えることに、付け加えて、
「子どもに、直接聞いてしまう」というやり方も、
時には、思い出していただき、考えて実践してみていただけたら、
子ども喜ぶと思います。
ぜひ、お勧めいたします。
お母さん、お父さん、日々実践。私も、がんばります。
2010年05月19日
6.お母さんとお父さんの意見が合わないでもOK
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

あなたの家族では、お母さんとお父さんの中に、
役割というのは、あるでしょうか?
役割と言うのは、
お母さんが「怒る役」、
お父さんが「ちやほやする役」だったり、
反対に、
お母さんが「褒める役」、
お父さんが「厳しくしつける役」だったりと、
家族によって違うと思います。
たとえば、私の家族の中での役割は、どちらかと言うと
、「ちやほやする役」だったり、「褒める役」だったり、するのですが、
(その役しかできないということが、大きい・・・)
私の代わりに「厳しい事を言ってくれる役」のお母さんの意見は、
原則的には、絶対に正しいと、
まずは、思うようにしています。
なぜなら、
私は、なかなか「厳しい役」が、演じられないからです。
かと言って、子どもに対する、厳しさと言う名の愛情が必要ないか?
と言えば、明確に、必要と考えているからです。
※ちなみに、私は、社員教育のプロなのですが、社員は、
厳しさと言う名の愛情が必要と考え、自ら実践しています。
子どもは、褒めて育てるべきか? 叱って育てるべきか?
という議論も、ありますが、
これは、褒めても、叱っても、どちらにも愛情があれば、
OKなように、
厳しく子どもに接するお父さんも、いつも優しいお母さんも、
両方のキャラクターとも子どもによっては、必要になるのです。
実は、私の本業の中に、
「経営者の考えている事を、社員の方にお伝えする」という仕事が、あります。
その中で、気がつくのは、
社長さんが、厳しい会社は、大番頭さんは優しい、
逆に、
社長が優しい会社は、大番頭さんは厳しいという、
別々のキャラクターのコンビの経営が上手くいっているという、ケースが多いのです。
社長は、大番頭のことを、尊重し、
大番頭も社長の言うことに、YESマンにばかりならず、自分の意見を主張する。
お互い意見が違うが、尊重し合える関係。
私と同じように、
子どもになかなか厳しく言えないお父さんも、いると思います。
そんなお父さんに限って、
お母さんが厳しく、子どもに接すると、ヒヤヒヤするかもしれません。
そして、思わず、「もっと優しくしろよ」と、
自分の考えを押し付けてしまうかも、しれません。
そんな時は、別々のキャラクターを演じるからこそ、
上手くいくケースも、思い出して下さい。
そして、お母さんの主張の状況の時は、
「そりゃ、お母さんの言うとおりだろ」と言う言葉を、言ってみると、
良いと思います。
お母さんの厳しさも認めたうえで、
私たちお父さんの意見も、応援してもらう。
世の中に出れば、多様な人がいます。
その意味では、お母さん、お父さんの意見が合わなくても、
お互い尊重し合えれば、
子どもにとっては、
社会に出る前の良いトレーニングの場になるのかもしれません。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

あなたの家族では、お母さんとお父さんの中に、
役割というのは、あるでしょうか?
役割と言うのは、
お母さんが「怒る役」、
お父さんが「ちやほやする役」だったり、
反対に、
お母さんが「褒める役」、
お父さんが「厳しくしつける役」だったりと、
家族によって違うと思います。
たとえば、私の家族の中での役割は、どちらかと言うと
、「ちやほやする役」だったり、「褒める役」だったり、するのですが、
(その役しかできないということが、大きい・・・)
私の代わりに「厳しい事を言ってくれる役」のお母さんの意見は、
原則的には、絶対に正しいと、
まずは、思うようにしています。
なぜなら、
私は、なかなか「厳しい役」が、演じられないからです。
かと言って、子どもに対する、厳しさと言う名の愛情が必要ないか?
と言えば、明確に、必要と考えているからです。
※ちなみに、私は、社員教育のプロなのですが、社員は、
厳しさと言う名の愛情が必要と考え、自ら実践しています。
子どもは、褒めて育てるべきか? 叱って育てるべきか?
という議論も、ありますが、
これは、褒めても、叱っても、どちらにも愛情があれば、
OKなように、
厳しく子どもに接するお父さんも、いつも優しいお母さんも、
両方のキャラクターとも子どもによっては、必要になるのです。
実は、私の本業の中に、
「経営者の考えている事を、社員の方にお伝えする」という仕事が、あります。
その中で、気がつくのは、
社長さんが、厳しい会社は、大番頭さんは優しい、
逆に、
社長が優しい会社は、大番頭さんは厳しいという、
別々のキャラクターのコンビの経営が上手くいっているという、ケースが多いのです。
社長は、大番頭のことを、尊重し、
大番頭も社長の言うことに、YESマンにばかりならず、自分の意見を主張する。
お互い意見が違うが、尊重し合える関係。
私と同じように、
子どもになかなか厳しく言えないお父さんも、いると思います。
そんなお父さんに限って、
お母さんが厳しく、子どもに接すると、ヒヤヒヤするかもしれません。
そして、思わず、「もっと優しくしろよ」と、
自分の考えを押し付けてしまうかも、しれません。
そんな時は、別々のキャラクターを演じるからこそ、
上手くいくケースも、思い出して下さい。
そして、お母さんの主張の状況の時は、
「そりゃ、お母さんの言うとおりだろ」と言う言葉を、言ってみると、
良いと思います。
お母さんの厳しさも認めたうえで、
私たちお父さんの意見も、応援してもらう。
世の中に出れば、多様な人がいます。
その意味では、お母さん、お父さんの意見が合わなくても、
お互い尊重し合えれば、
子どもにとっては、
社会に出る前の良いトレーニングの場になるのかもしれません。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
2010年05月08日
5.頭の良いお父さん、おバカなお父さん。
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

実は、私の本業の中に、
「経営者の考えている事を、社員の方にお伝えする」
という仕事が、あります。
その仕事をしていると、
「頭の良い経営者(上司)の方と、おバカな経営者(上司)の方の致命的な違い」
に遭遇することが、あります。
今日は、そのようなお話から入ります。
その、頭の良い経営者(上司)の方と、
おバカな経営者(上司)の方の致命的な違いが、
あらわれるのは、意外と思われるかもしれないですが、
実は、「会社の状況が良い時」つまり、商売がうまくいっている時とか、
上司が昇進した時とか、
とにかく、「良い状態」のとき、にあらわれるのです。
頭の良い経営者(上司)は、
そのような時に、その手柄を、社員さんや部下の方のおかげだと、言います。
社員さんや部下も、
「本当は、お世辞で言ってくれているとか」、
「そこまで、感謝されなくても・・・」とか、
少し照れて、ムズかゆい思いがしているのは、わかっているのです。
でも、「かなり、嬉しい」のです。
嬉しくて、ますますその経営者や上司のために、がんばろうと、
思うのです。
それが、良い循環になり、益々良いことが起こります。
しかし、おバカな経営者(上司)は、手柄を独り占めにします。
「俺がすごいからだ」と言い放ち、
中には、
このようなせっかくの良い機会に、「俺に比べ、社員(部下)は、全くダメだ」などと、
おバカなことを、言ってしまう傾向があるのです。
お分かりのように、このような経営者(上司)は、
継続して、成功し続けることは、できません。
なぜなら、
上司が成功すればするほど、自慢を聞かされるし、お前はダメだと、言われるのですから、
メンバーは無意識に「もう協力したくない」と思うからです。
同じような事が、家族にも、言えます。
頭の良い、お父さん、お母さんは、
何か良いことがあった時に、お父さんなら、お母さんのおかげ、子どものおかげと、
感謝するのです。
それに対し、
おバカなお父さん、お母さんは、何か誇らしげなことが起きた時に、
お父さんなら、「俺がこんなに頑張っているのに、お前は!」
とお母さん、子どもを敵に回すようなことを、言ってしまうのです。
家族の場合で言えば、企業とは違い、
家族の状況が、ジェットコースターのように、乱高下することは、ないでしょうから、
普段、普通に健康で、何事もなく生活している事自体が、
実は幸せなことです。
お父さんは、お父さんの最大のサポーターであるお母さんや子どもに感謝し、
お母さんは、お母さんの最大のサポーターである、お父さんや子どもに感謝するのが、
おバカにならない秘訣なのです。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

実は、私の本業の中に、
「経営者の考えている事を、社員の方にお伝えする」
という仕事が、あります。
その仕事をしていると、
「頭の良い経営者(上司)の方と、おバカな経営者(上司)の方の致命的な違い」
に遭遇することが、あります。
今日は、そのようなお話から入ります。
その、頭の良い経営者(上司)の方と、
おバカな経営者(上司)の方の致命的な違いが、
あらわれるのは、意外と思われるかもしれないですが、
実は、「会社の状況が良い時」つまり、商売がうまくいっている時とか、
上司が昇進した時とか、
とにかく、「良い状態」のとき、にあらわれるのです。
頭の良い経営者(上司)は、
そのような時に、その手柄を、社員さんや部下の方のおかげだと、言います。
社員さんや部下も、
「本当は、お世辞で言ってくれているとか」、
「そこまで、感謝されなくても・・・」とか、
少し照れて、ムズかゆい思いがしているのは、わかっているのです。
でも、「かなり、嬉しい」のです。
嬉しくて、ますますその経営者や上司のために、がんばろうと、
思うのです。
それが、良い循環になり、益々良いことが起こります。
しかし、おバカな経営者(上司)は、手柄を独り占めにします。
「俺がすごいからだ」と言い放ち、
中には、
このようなせっかくの良い機会に、「俺に比べ、社員(部下)は、全くダメだ」などと、
おバカなことを、言ってしまう傾向があるのです。
お分かりのように、このような経営者(上司)は、
継続して、成功し続けることは、できません。
なぜなら、
上司が成功すればするほど、自慢を聞かされるし、お前はダメだと、言われるのですから、
メンバーは無意識に「もう協力したくない」と思うからです。
同じような事が、家族にも、言えます。
頭の良い、お父さん、お母さんは、
何か良いことがあった時に、お父さんなら、お母さんのおかげ、子どものおかげと、
感謝するのです。
それに対し、
おバカなお父さん、お母さんは、何か誇らしげなことが起きた時に、
お父さんなら、「俺がこんなに頑張っているのに、お前は!」
とお母さん、子どもを敵に回すようなことを、言ってしまうのです。
家族の場合で言えば、企業とは違い、
家族の状況が、ジェットコースターのように、乱高下することは、ないでしょうから、
普段、普通に健康で、何事もなく生活している事自体が、
実は幸せなことです。
お父さんは、お父さんの最大のサポーターであるお母さんや子どもに感謝し、
お母さんは、お母さんの最大のサポーターである、お父さんや子どもに感謝するのが、
おバカにならない秘訣なのです。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
2010年04月30日
4.目的を必ず達成する、お母さん、お父さんの共通点・・・
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

今日は、覚えておいていただきたい事が、一つだけ、あります。
それは
、「脳は、確実に質問されたことに対し、答えを出す」
ということです。
これだけでは、どのように、
子どもの潜在能力を伸ばすことにつながるのか?
わかりづらいので、少し順を追って、
説明していきましょう。
私の本業の一つに、
ビジネスにおいての社員教育などが、あります。
そのときに、発展途上でまじめな社員さんほど、
自分自身に、
「なぜ、私は仕事ができないのだろう」
という、不適切な質問を、してしまう傾向があります。
なぜこのような質問が、不適切かと言うと、
「脳は、確実に質問されたことに対し、その答えを出してしまう」
からなのです。
「私が、ダメな人間だから」
「上司が悪いから」
などなど、様々な回答で悩みます。
発展途上で、真面目な社員さんほど、そのように、
自分を追い込んでしまいます。
大事なことは、このようなことが、
事実かそうでないかと言うことでなく、このような答えでは、
「仕事ができないと感じている事実」
が、なにも変わらない。
その事が、問題なのです。
では、ビジネスで成功している人は、どのような質問をしているのか?
というと、
全く違う質問を自分自身にします。
その質問とは、
「どうしたら、仕事ができるようになるのだろう」です。
そして、この質問を脳が、キャッチした瞬間に、脳は、
望むか望まないか?
にかかわらず、その答えを探しはじめてしまいます。
「もっと、注意深く行えば、できる」
「上司に、相談すればできる」
同じようなことが、子育て中のお母さんお父さんにも、言えます。
「なぜ、子どもを怒ってしまうのだろう」
とか
「なぜ、うちの子は、そそっかしいのだろう」
など、という質問を、脳にすれば、
「私は、ダメな母親だから?」
「うちの子は、ダメな子?」
「旦那が協力的ではないから」
という何も解決に導かない、回答が出てくるかもしれません。
それでは、せっかくした質問が、解決へと導かないので、
好ましくないのです。
そうではなく、
「どうしたら、子どもを怒らず、目的を達成できるかな」
とか、
「どうしたら、落ち着いて、子どもが集中するかな」
という質問をすると、脳は、瞬間的にその答えを探しはじめ、やがて、
私たちに、回答をもたらすでしょう。
その回答は、いわゆる、「工夫」や「新しいアイデア」といったものです。
工夫や、アイデアが出てくれば、またそれを、
実行に移してみる、チャレンジ、TRYしてみることが、できるのです。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

今日は、覚えておいていただきたい事が、一つだけ、あります。
それは
、「脳は、確実に質問されたことに対し、答えを出す」
ということです。
これだけでは、どのように、
子どもの潜在能力を伸ばすことにつながるのか?
わかりづらいので、少し順を追って、
説明していきましょう。
私の本業の一つに、
ビジネスにおいての社員教育などが、あります。
そのときに、発展途上でまじめな社員さんほど、
自分自身に、
「なぜ、私は仕事ができないのだろう」
という、不適切な質問を、してしまう傾向があります。
なぜこのような質問が、不適切かと言うと、
「脳は、確実に質問されたことに対し、その答えを出してしまう」
からなのです。
「私が、ダメな人間だから」
「上司が悪いから」
などなど、様々な回答で悩みます。
発展途上で、真面目な社員さんほど、そのように、
自分を追い込んでしまいます。
大事なことは、このようなことが、
事実かそうでないかと言うことでなく、このような答えでは、
「仕事ができないと感じている事実」
が、なにも変わらない。
その事が、問題なのです。
では、ビジネスで成功している人は、どのような質問をしているのか?
というと、
全く違う質問を自分自身にします。
その質問とは、
「どうしたら、仕事ができるようになるのだろう」です。
そして、この質問を脳が、キャッチした瞬間に、脳は、
望むか望まないか?
にかかわらず、その答えを探しはじめてしまいます。
「もっと、注意深く行えば、できる」
「上司に、相談すればできる」
同じようなことが、子育て中のお母さんお父さんにも、言えます。
「なぜ、子どもを怒ってしまうのだろう」
とか
「なぜ、うちの子は、そそっかしいのだろう」
など、という質問を、脳にすれば、
「私は、ダメな母親だから?」
「うちの子は、ダメな子?」
「旦那が協力的ではないから」
という何も解決に導かない、回答が出てくるかもしれません。
それでは、せっかくした質問が、解決へと導かないので、
好ましくないのです。
そうではなく、
「どうしたら、子どもを怒らず、目的を達成できるかな」
とか、
「どうしたら、落ち着いて、子どもが集中するかな」
という質問をすると、脳は、瞬間的にその答えを探しはじめ、やがて、
私たちに、回答をもたらすでしょう。
その回答は、いわゆる、「工夫」や「新しいアイデア」といったものです。
工夫や、アイデアが出てくれば、またそれを、
実行に移してみる、チャレンジ、TRYしてみることが、できるのです。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
2010年04月28日
3.お父さん必見 一石二鳥の 「子どもを褒めるスキル」
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

人をやる気にさせ、
その人がチャレンジと成功体験を積みかさねていく、
お手伝いをする手段に、
「人を褒める」というスキルがあります。
人は、誰かに褒められると、とてもうれしいものですし、
褒められた本人は、やる気がでてきて、モチベーションが、あがります。
「褒める」ことは、確かに、とても重要な事なのです。
この「褒める」と言うスキルは、
子どもとのコミュニケーションに配慮し、気をつけながら生活をしている、
お母さん、お父さんにとっては、
「非常に重要である」事は、
誰でも一度は、聞いたことがあることだと思います。
しかし、実際に、知っているのとやれるのは別の話。
実際にこのスキルを使いこなしている、
お母さん、お父さんがいるのか?というと、私自身も耳の痛くなる話で、少ないのかもしれません。
私の本業の一つは、
実は、社員教育なのですが、
いわゆる業績が良い会社の経営者や、大企業の上司の方でさえも、
「社員の方を褒める」、「部下の方を褒める」
と言うスキルを上手く使いこなせず、大変な苦労をされている方が、多いようです。
ですから、
これが、毎日顔を合わせ、また、ビジネスライクでは行かない、
いろいろな感情が入り混じる家族関係の中では、
「褒める」ということを、実践することは、
なおさらチャレンジなことかもしれません。
そこで、今日は特にお父さんが、
簡単に「褒める」を実践し、そして、同時にお母さん、お父さんのカブが上がり、
子どもがやる気になるスキルを、ご紹介します。
ぜひ、普段の生活で、実践してみてください。
通常、お父さんが「褒める」というと、
お父さんが、子どもを褒めることを連想します。
しかし、お父さんは、普段家にはいないですし、
日々子どもとの接点がなくなる傾向にありますから、子どもの事が良く分からないかもしれません。
そのような状態で、褒めても、ポイントが外れるだけです。
子どもは、直感力が鋭いですから、
適当に褒めても、見破られるだけなのです。
お父さんは、お母さんの力を借りるのです。
お母さんに、子どもの最近の良いところ、褒められそうな所を聞き出し、
そして、お父さんは子どもに、
「お母さんが、○○○で褒めていたぞ。お父さんも嬉しかった」
と伝聞調で伝えるようにするのです。
(子どもの年齢があがるごとに、お父さんの演技力が必要です 笑)
1.お母さんとお父さんの会話が生まれ、
2.お母さんが、ついつい褒め忘れたことを、お父さんがフォローしてくれ、
3.子どももお父さんから、伝聞調で褒められている事をしれば、
なお嬉しくやる気になる。全循環になる。
というのが、私の仮説で実践しています。
さて、この文章を読んでくださっているのは、
お母さんが多いかと思います。
ぜひ、この文章を、お父さんに転送して、
見せてあげて、お父さんに手柄を与えてあげてください。
普段、仕事で忙しいお父さんも、お母さんのためになり、
子どものためになるなら、ひと肌脱がれるかもしれません。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

人をやる気にさせ、
その人がチャレンジと成功体験を積みかさねていく、
お手伝いをする手段に、
「人を褒める」というスキルがあります。
人は、誰かに褒められると、とてもうれしいものですし、
褒められた本人は、やる気がでてきて、モチベーションが、あがります。
「褒める」ことは、確かに、とても重要な事なのです。
この「褒める」と言うスキルは、
子どもとのコミュニケーションに配慮し、気をつけながら生活をしている、
お母さん、お父さんにとっては、
「非常に重要である」事は、
誰でも一度は、聞いたことがあることだと思います。
しかし、実際に、知っているのとやれるのは別の話。
実際にこのスキルを使いこなしている、
お母さん、お父さんがいるのか?というと、私自身も耳の痛くなる話で、少ないのかもしれません。
私の本業の一つは、
実は、社員教育なのですが、
いわゆる業績が良い会社の経営者や、大企業の上司の方でさえも、
「社員の方を褒める」、「部下の方を褒める」
と言うスキルを上手く使いこなせず、大変な苦労をされている方が、多いようです。
ですから、
これが、毎日顔を合わせ、また、ビジネスライクでは行かない、
いろいろな感情が入り混じる家族関係の中では、
「褒める」ということを、実践することは、
なおさらチャレンジなことかもしれません。
そこで、今日は特にお父さんが、
簡単に「褒める」を実践し、そして、同時にお母さん、お父さんのカブが上がり、
子どもがやる気になるスキルを、ご紹介します。
ぜひ、普段の生活で、実践してみてください。
通常、お父さんが「褒める」というと、
お父さんが、子どもを褒めることを連想します。
しかし、お父さんは、普段家にはいないですし、
日々子どもとの接点がなくなる傾向にありますから、子どもの事が良く分からないかもしれません。
そのような状態で、褒めても、ポイントが外れるだけです。
子どもは、直感力が鋭いですから、
適当に褒めても、見破られるだけなのです。
お父さんは、お母さんの力を借りるのです。
お母さんに、子どもの最近の良いところ、褒められそうな所を聞き出し、
そして、お父さんは子どもに、
「お母さんが、○○○で褒めていたぞ。お父さんも嬉しかった」
と伝聞調で伝えるようにするのです。
(子どもの年齢があがるごとに、お父さんの演技力が必要です 笑)
1.お母さんとお父さんの会話が生まれ、
2.お母さんが、ついつい褒め忘れたことを、お父さんがフォローしてくれ、
3.子どももお父さんから、伝聞調で褒められている事をしれば、
なお嬉しくやる気になる。全循環になる。
というのが、私の仮説で実践しています。
さて、この文章を読んでくださっているのは、
お母さんが多いかと思います。
ぜひ、この文章を、お父さんに転送して、
見せてあげて、お父さんに手柄を与えてあげてください。
普段、仕事で忙しいお父さんも、お母さんのためになり、
子どものためになるなら、ひと肌脱がれるかもしれません。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
2010年04月27日
2.「心と言葉の関係」=「体と食事の関係」
こんにちは。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

前回は、
・「グズグズするな」
・「アイスクリームを食べるな」
・「おもちゃを買うな」
・「鼻をほじるな」
・「夜更かしするな」
・「泣くな」
お母さん、お父さんが日々の生活の中で、子どもに使う、
これら全ての禁止ワード
「○○するな」が、
実は、子どもにとってみると、
「○○しなさい」という、
命令ワードになっていることを、ご存知ですか?
というお話をしました。
つまり、禁止したつもりの言葉の全てが、脳の構造から逆算すると、
命令したことに、なってしまう。
つまり・・・
・「グズグズしなさい」
・「アイスクリームを食べなさい」
・「おもちゃを買いなさい」
・「鼻をほじりなさい」
・「夜更かししなさい」
・「泣きなさい」
という事と、同じということになるという、
説明をしました。
今回は、では、
「どのような声かけフレーズをすれば、子どもにとってイメージがわきやすいのか?」
ということを、お話したいと、思います。
たとえば、私たちの子どもが、グズグズしていたとします。
そのような時に、
お母さん、お父さんにとってNGなのは、
「グズグズしないで、宿題をしなさい!」
と、言うことです。
そうではなく、このような時は、まずは、お母さんお父さんにとって、
子どもに「なって欲しい状態」を、
イメージするようにしていただくと、間違いがないと思います。
そのような状態は、どのような状態でしょうか?
たとえば、
「テキパキして、集中して宿題を行っている状態」
かもしれませんし、
「スピーディーに、次から次へと、ページをめくっている映像」
かもしれません。
お母さん、お父さんは、このような
「なって欲しい状態の映像を、言語化して伝える」
ことを、意識していただくと、子どもに真意が伝わりやすくなります。
「きびきび、テキパキ、宿題が済めば楽しいね」
とか、
「次から次へと、早く済んでしまえば、すっきりするね」
とか、
「集中してやろうね。時間をはかってみようか?」
とか、
慣れてくれば、このような肯定的な表現が、
次第に出来るかも知れません。
「心と言葉の関係」は、「体と食事の関係」に似ています。
毎日栄養のある食事を取っていると、
そのことが体に反映されていきますが、毎日出来るだけポジティブな言葉を、
お母さんお父さんから、浴びせられていると、
そのことが次第に心に反映されてくるようになるのでしょう。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。
ふれなび代表の HIROSHI AMIKURAです。

前回は、
・「グズグズするな」
・「アイスクリームを食べるな」
・「おもちゃを買うな」
・「鼻をほじるな」
・「夜更かしするな」
・「泣くな」
お母さん、お父さんが日々の生活の中で、子どもに使う、
これら全ての禁止ワード
「○○するな」が、
実は、子どもにとってみると、
「○○しなさい」という、
命令ワードになっていることを、ご存知ですか?
というお話をしました。
つまり、禁止したつもりの言葉の全てが、脳の構造から逆算すると、
命令したことに、なってしまう。
つまり・・・
・「グズグズしなさい」
・「アイスクリームを食べなさい」
・「おもちゃを買いなさい」
・「鼻をほじりなさい」
・「夜更かししなさい」
・「泣きなさい」
という事と、同じということになるという、
説明をしました。
今回は、では、
「どのような声かけフレーズをすれば、子どもにとってイメージがわきやすいのか?」
ということを、お話したいと、思います。
たとえば、私たちの子どもが、グズグズしていたとします。
そのような時に、
お母さん、お父さんにとってNGなのは、
「グズグズしないで、宿題をしなさい!」
と、言うことです。
そうではなく、このような時は、まずは、お母さんお父さんにとって、
子どもに「なって欲しい状態」を、
イメージするようにしていただくと、間違いがないと思います。
そのような状態は、どのような状態でしょうか?
たとえば、
「テキパキして、集中して宿題を行っている状態」
かもしれませんし、
「スピーディーに、次から次へと、ページをめくっている映像」
かもしれません。
お母さん、お父さんは、このような
「なって欲しい状態の映像を、言語化して伝える」
ことを、意識していただくと、子どもに真意が伝わりやすくなります。
「きびきび、テキパキ、宿題が済めば楽しいね」
とか、
「次から次へと、早く済んでしまえば、すっきりするね」
とか、
「集中してやろうね。時間をはかってみようか?」
とか、
慣れてくれば、このような肯定的な表現が、
次第に出来るかも知れません。
「心と言葉の関係」は、「体と食事の関係」に似ています。
毎日栄養のある食事を取っていると、
そのことが体に反映されていきますが、毎日出来るだけポジティブな言葉を、
お母さんお父さんから、浴びせられていると、
そのことが次第に心に反映されてくるようになるのでしょう。
お母さん、お父さん、日々実践。
私もがんばります。